2025年1月にDFreeを導入いただいたサニープレイス彦根さま。
生産性向上委員会 委員長の北村和也さまをはじめ、メンバーの皆さまを中心に特養9ユニット、ショートステイ1ユニットの全10ユニットでご活用いただいております。
2025年8月、導入後半年間の成果を振り返る会議を開催しました。
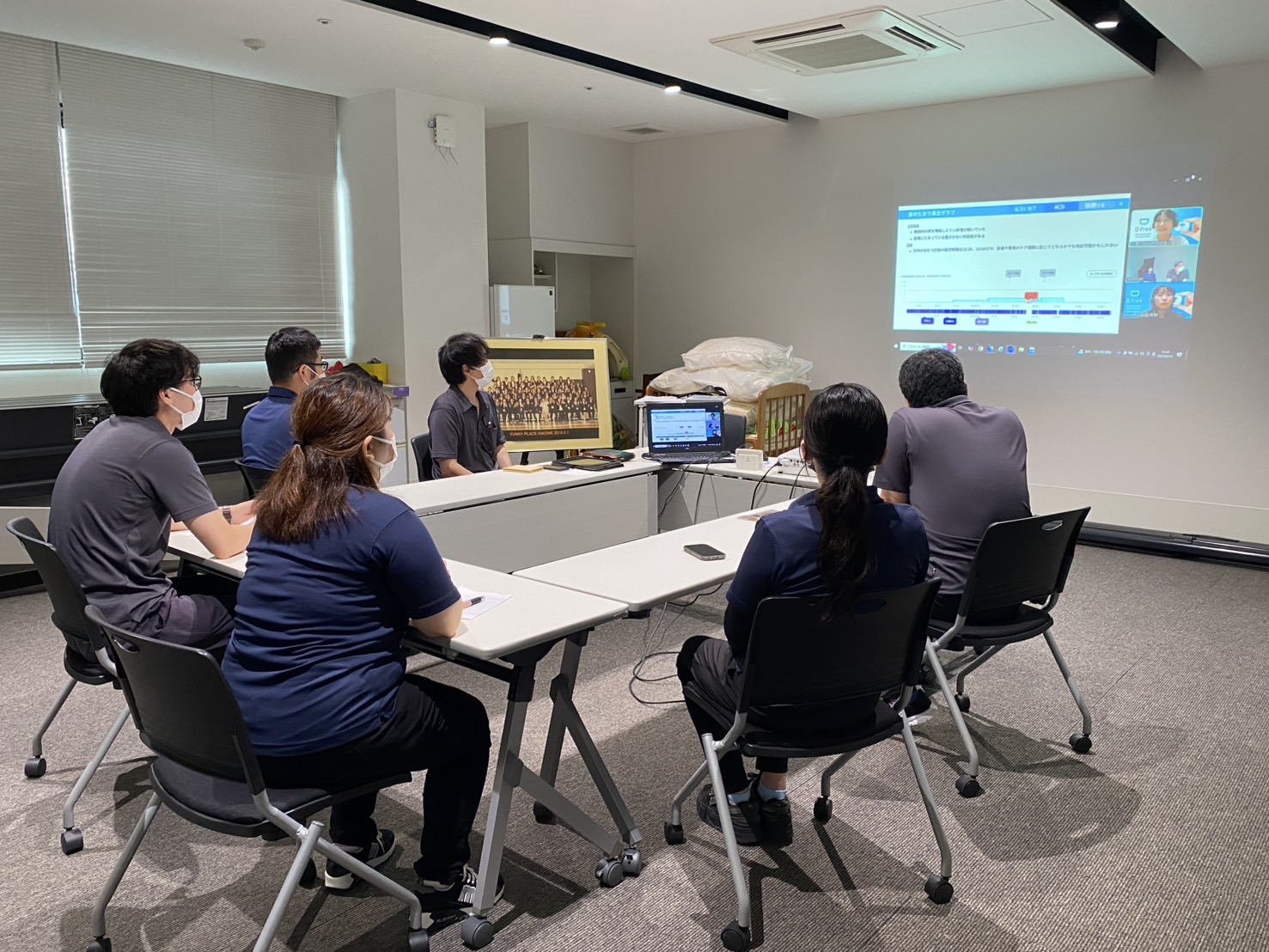
職員負担軽減と利用者の自立支援を両立するためDFree導入
サニープレイス彦根さまでのDFree導入前の課題は次のようなものでした。
- タイミングが合わずに全更衣が増えてくると、職員の負担になること
- トイレ誘導の定時で間に合っていた方でも、漏れが増えていること
- おむつ交換の方でもタイミングが合わないことがあること
- 夜間のトイレ誘導のタイミングや行動要因がわからない方がいらっしゃること
膀胱の状態を把握し、適切なタイミングでケアを行うことで業務負担を軽減する目的で、DFree導入を決定しました。
データを基にケア方法を最適化
サニープレイス彦根さまではDFreeを5台導入。これまでに合計24名(うち8名はトライアル時)のご利用者さまに約2週間ずつDFreeを装着しました。
膀胱の状態をモニタリングし、「排尿傾向分析」「活動傾向分析」レポートを出力。これを基にケア方法を見直しています。
また、生産性向上委員会を毎月開催し、弊社カスタマーサクセス・営業も参加。各ユニットの委員から使用状況や結果のフィードバックを行い、個別のケア方針を検討しています。
生産性向上委員長の北村さまは、運用の工夫について次のように話します。
ー 導入時に委員会内でキックオフ研修を受講し、まず各ユニットの委員が使用方法を理解するところから始まりました。新しい機器の導入に苦手意識がある職員にも受け入れてもらえるように、委員が自身のユニットに戻った際には使用方法からではなく“「こんなことができるようになる」”という得たい結果の周知から入るよう心掛けました。
ー 継続して活用するために、委員だけでなく介護リーダーにも積極的な介入を依頼し、現在課題が見えている利用者だけを対象とするのではなく、より良いケアの提供を目的に「課題を見つける」ことができるよう全利用者を対象とすることを周知しました。
ケア時間の調整や誘導精度が向上し、職員への説明も容易に
会議内ではDFreeを使用することで状況が改善したケースについて次のような報告がありました。
”それまで決めていた排泄時間で入ってもパッドが濡れていなくて、次に介助に入ったときには衣類交換が必要だった方にDFreeを使用しました。出たタイミングが視覚的にわかるようになったので、排泄介助の時間を変えさせてもらいました。介助の時間を合わせられるようになったので、その方にはかなり有効的に使わせてもらえました。ただ、排尿パターンもその都度変わってきてしまうので、本当はもう少し継続使用したかったなと思っています。”
”トイレ誘導のタイミングが全く分からない状態で入所された方に対し、DFreeのレポートが目安になり大変助かりました。”
”入居者さんだけではなくて、職員的にも有り難かったです。今までいるメンバーは経験則でこの時間にケアに入ろうって言っていたのを、DFreeを使うことで明確に「この時間のほうが良い」「この時間に誘導します」と説明がしやすくなりました。”

今後の展望
北村さまは、今後のDFree活用について次のように話します。
ー 排泄介助の質の向上については既に効果を感じていますが、“定時誘導”の“定時”が利用者によって違う、排泄個別ケアに到達できればと考えています。
ー 今後広げていきたい方向性としては「認知症利用者への対応」に役立たすことを模索しています。認知症利用者の行動・心理症状出現は、尿意など排泄が関係しているのではと仮定することも多いのですが、これまでは症状が出現してから排泄の声掛けを行い確認していました。DFreeを活用し、意思疎通が難しい認知症利用者に適切なタイミングで排泄介助を行うことで行動・心理症状の出現を防ぐことはできるのか。DFreeのデータと利用者の気持ちの変化との連動を観察していけば、実現可能なのではないかと期待しています。
サニープレイス彦根さまは、DFreeのデータに基づくケア改善サイクルをユニット全体で回している点が大きな特徴です。導入前の課題を明確化し、運用体制を整えることで、利用者のQOL向上と職員の業務効率化を同時に実現されています。
弊社では今後も、各施設さまの現場状況に合わせた活用提案やデータ分析のお手伝いをさせていただき、より多くの現場での排泄ケアの課題解決や成功体験を目指していけたらと考えております。
DFreeのお試しはこちらから
